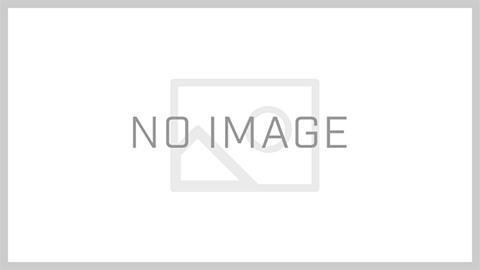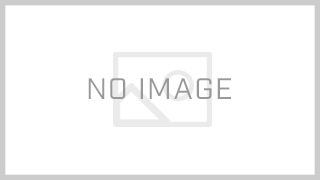薬学部の5年次に行われるOSCE(客観的臨床能力試験)は、CBTと並ぶ実習前の重要関門。「知識の試験」だったCBTとは違い、OSCEは実技+コミュニケーション能力+対応力が問われます。
でも正直、OSCEは緊張との戦い。
「覚えていたはずなのに言葉が出てこない…」
「沈黙の空気に耐えられない…」
そんな経験、ありませんか?
この記事では、実際のOSCE本番での“やらかし”体験談をもとに、「こうしておけばよかった」と感じた具体的な対策法をお届けします。薬学生本人はもちろん、保護者の方も「こんな試験なんだ」と知っておくと安心です。
ケース1|緊張であいさつを飛ばす → 減点&場の空気がギクシャク…
OSCEの基本は「最初の声かけ」から。私は当日、緊張のあまり頭が真っ白になり、「こんにちは。薬剤師の○○です」の一言を忘れたままいきなり説明を始めてしまいました。
相手(模擬患者)の表情も固まり、出だしからペースが崩れてしまいました…。
対策法:あいさつ文は“セリフ”として丸暗記!
「こんにちは。薬剤師の○○です。本日はお時間をいただきありがとうございます。」
このようなテンプレ文を繰り返し練習して、自然に口から出る状態にしておくことが大切です。
ケース2|沈黙にパニック→勝手に話し続けてしまう
服薬指導中、模擬患者が無言になったタイミングで、私は「えっ、何か間違えた?」と焦り、確認もせずに説明を続けてしまいました。結果、相手の理解度も気持ちも無視してしまう形に。
実は沈黙=失敗ではなく、「理解中」「質問を考え中」のサインだったりします。
対策法:沈黙を恐れず、“確認ワード”を使う!
「ここまでのご説明でご不明な点はありますか?」
「何か気になることがあれば、遠慮なくおっしゃってくださいね。」
こんな一言を挟むだけで、双方向の信頼感がぐっと高まります。
ケース3|副作用を聞かれて頭真っ白 → 思わず「わかりません」
「この薬の副作用って何ですか?」という質問に、「えーと…あれ…なんだっけ」と考えているうちに時間が経過し、最終的に**「ちょっと分からないです」と言ってしまった**経験があります。
実際には覚えていたのに、とっさの緊張で言葉が出てこなかったのが原因でした。
対策法:予測質問リストを作ってシミュレーション!
よく聞かれる副作用・併用禁忌・飲み忘れ時の対応など、定番質問は事前にリスト化し、答える練習をしておきましょう。
ボソボソ話すより、「少々お待ちください、確認します」と堂々と対応したほうが好印象です。
ケース4|手技を飛ばす・順番を間違える → 焦ってどんどん空回り
実技試験(吸入指導や血圧測定など)では、**「この順番でやる」と頭でわかっていても、体がついてこない」**ということがよく起こります。
例えば吸入指導で「キャップを外す」→「しっかり吸入」→「うがい」など、“流れ”として覚えていないとミスが出やすいです。
対策法:動画やチェックリストで“手順を視覚化”して練習!
実際に声に出して・手を動かして練習することで、「知識」から「実技」に変わります。
大学によってはOSCE練習動画を配布しているところもあるので、それをフル活用するのがおすすめです。
まとめ|OSCEは「準備すれば防げるミス」が多い
CBTは“知識戦”、OSCEは“人間力戦”とも言えます。
でも、今回紹介したようなミスはほとんどが事前の練習でカバーできます。
- 定型文を暗記して「緊張時も言えるように」
- 沈黙や質問への“反応”を想定しておく
- 手技の“順番”は体で覚えるまで反復
本番は誰でも緊張します。でも、準備してきたことはちゃんと身についています。
自信を持って、堂々とした態度で臨んでくださいね!